将来が不安だから、老後が心配だから。
私もそう思って、せっせとお金を貯めたり、投資を勉強したりしてきました。
でも『きみのお金はだれのため』を読んで、私はふと立ち止まりました。
お金がいくらあっても、それを生かしてくれる人がいなかったら、何も手に入らない。
この当たり前のような事実に、深く心を揺さぶられたのです。
- 「お金があっても不安」はどうして?
- 年金がピンチって聞くけど、本当の原因は?
- これからは“ありがとう”を込めたお金の使い方が大事
お金があれば、安心。そう思っていたはずなのに
“老後が心配だから貯金を”
“投資をしておかないと将来が不安”
ずっとそう思ってきました。
でもこの本に書かれていたのは、
年金制度が壊れる本当の理由は「お金」じゃなく、「人がいなくなること」だということ。
お金をいくら持っていても、
そのお金を受け取って動いてくれる人がいなければ、何も得られない。
お金は万能じゃない。
人がいてこそ、お金には意味が宿る。
それを、私たちは忘れかけていたのかもしれません。
年金制度が壊れそうなのは、「お金が足りないから」じゃなかった

本の中で印象的だったのは、年金制度の話でした。
「もらえなくなるかもしれない」
「払うだけ損だ」
そんな声をよく聞くけれど、実は問題の本質は“お金の不足”ではなかったのです。
少子化によって、生産する人=支える人がいなくなること。
年金というのは、今働く人が、今の高齢者を支えて成り立つ仕組み。
だからこそ、“お金”以上に“人”が重要なのだと、本は語ります。
だから少子化問題がここまで大切なんだと、曖昧に理解していたところの答えがわかりました。
200円でどら焼きを買ったのか、それとも「作ってもらった」のか
たとえば、コンビニでどら焼きを買ったとき。
200円払ってレジを通せば、それは“自分のもの”になります。
でも、そこには本当は無数の手がある。
作った人、包んだ人、運んだ人、陳列した人――
誰かの仕事が、日々の暮らしを支えてくれている。
この感覚を持てるかどうかで、お金の意味はまったく変わってきます。
なのに私たちは、お金を払った瞬間に「これは自分のものだ」と思ってしまう。
「お金がすべてを解決してくれた」と思い込んでしまう。
私たちは気づかないうちに、“お金で解決した気になって”、人の存在を見失っていたのかもしれません。
貯めこむだけでは、社会は回らない
「不安だから貯金する」
「節約して無駄遣いを減らす」
それ自体は悪いことじゃない。
でも、みんなが同じことをし続けたら、どうなるんだろう?
誰も物を買わなくなったら、働く人にお金が回らない。
企業が縮小すれば、仕事が減る。
そして、ますます不安が増えていく。
お金は、“使うことで誰かの役に立ち”、まためぐっていくもの。
その循環を信じることが、私たちの安心にもつながるのだと思いました。
私たちはみんな、誰かの役に立っている
働く人だけじゃない。
家を守る人、子どもを育てる人、地域に関わる人。
お金を稼ぐことだけが「価値」じゃない。
社会は、たくさんの“目に見えにくい支え”で成り立っています。
なのに、いつの間にか
「たくさん稼ぐ人が偉い」「お金を持っている人が勝ち組」
そんな価値観に縛られていなかったでしょうか。
本当は、どんな立場の人も、すでに誰かのために生きている。
その事実に、もっと目を向けて、感謝しながら暮らしていきたいですよね。
「ありがとう」を込めて、お金を使うということ
本を買うとき、便利だからネットで済ませる。
でも、町の本屋さんが閉店したとき、私は胸が痛みました。
あの場所に、棚に囲まれて、偶然出会った本たち。
本屋さんが“ある”ことが、どれだけ幸せなことだったか。
「ここに本屋があってくれて、ありがとう」
その気持ちで本屋で買うということが感謝であり、意思表示につながりますよね。

お金を落とすってこういうことですよね。
投資もそう。
外国株もいいけれど、私はやっぱり、日本の企業や人を信じたい。
だから、個別株も持ち続けようと思いました。

日本人が円を使っていかないと寂しいですよね。
お金は、つながりの“気配”を忘れさせる。でも…
私たちは、現代社会の中で、お金とともに生きています。
でもそのお金が、“誰か”の仕事の上にあることを、見えなくしてしまっているのも事実です。
「お金さえあれば」と思い込むことで、
“つながり”や“感謝”が、少しずつ消えていく。

それって寂しいことですよね。
でも――。
どら焼きを「誰かが作ってくれた」と思えるようになったとき、
私たちの暮らしは、少しだけ優しくなる気がするのです。
「みんなが支え合っている」って、想像以上に心強い
この本を読んで思ったのは、

不安って、「一人でなんとかしなきゃ」と思うから大きくなるんだな。
ということ。
でも、「みんなで支え合う」
そう思えたとき、ふっと心が軽くなりました。
不足していても、分け合えば、回る。
支え合えば、安心はつくれる。
完璧じゃなくても、成り立っていく。
そんな希望を、この本から受け取った気がします。
まとめ:お金は、感謝のカタチ。つながりの証
お金って、つい“数字”として見てしまうけれど、
本当は、「ありがとう」「あなたに託したい」という想いが込められるもの。
だから私はこれから、
自分が何にお金を使うか、誰に託すかを、丁寧に考えていきたいと思います。
スーパーで野菜を買うときも。
誰かに贈り物をするときも。
投資をするときも。
全部、「ありがとう」の気持ちをのせて。

『きみのお金はだれのため』は、
そんなことを思い出させてくれた、かけがえのない一冊になりました。
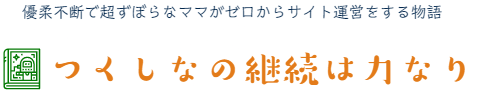
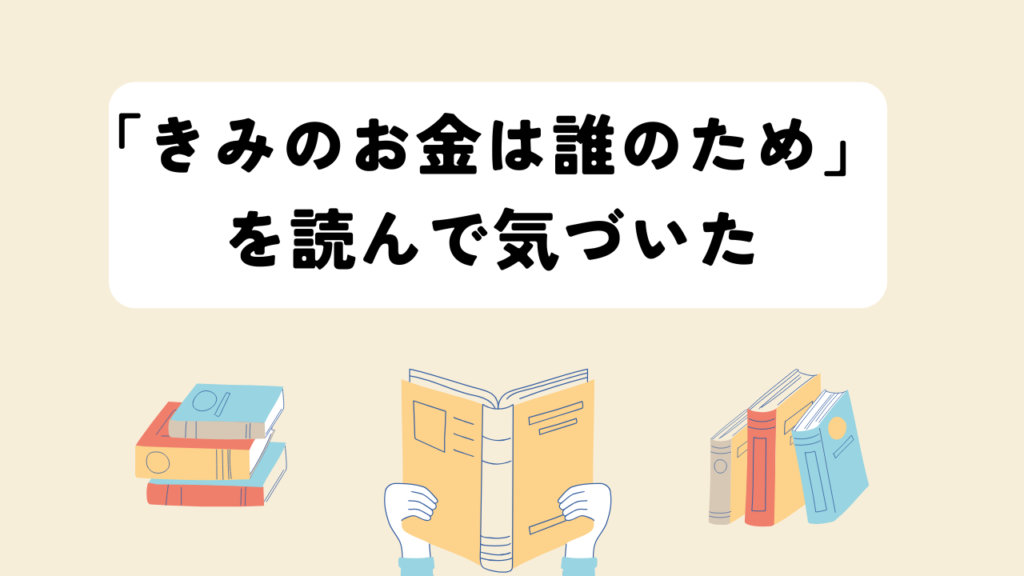
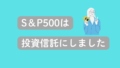

コメント